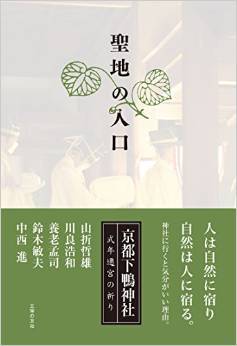2014年12月12日
京都検定にむけて・その6
昨日丸一日ゆっくりしていたので、本日は熱も下がり調子も快復して参りました。
試験まであと二日。用心しながらも頑張らないと
数年前に京都検定2・3級受験用に購入したもの
 マークシート専用のシャープペンシルと芯、そして消しゴム
マークシート専用のシャープペンシルと芯、そして消しゴム

別に普通のシャープペンシルや鉛筆でもいいのですが
「専用」という言葉に弱くて、こういう便利グッズについ手がのびてしまいました
これで記入するときちんと答えが繁栄されそうな気がします。
試験当日、3級は10時から各会場にて諸説明がはじまり、
マークシートの答案用紙に会場や受験番号もろもろを書き込み、
少しおいて大体10時15分あたりから試験開始です。
私の場合、まずは問題をざっと解き、答えと思われるものに○。
問題用紙プリントの四択の中の番号に直接○をつけています。
(こうしておくとあとで何に○をつけたか自己採点する際に都合がよい)
一通り解き終えたら最初のページに戻り、もう一度ゆっくりと確認。
四択の四つの言葉を一つずつしっかりと見て品定め。
案外思い込みや早とちりで最後までよく読まずにパパッと答えを判断していることがあり
後でよく考えると「なんでこの答えにしてしまったんだろう」と後悔すること多し。
なのでこのときに本当にそれで間違いがないかどうか、
四つをしっかりとみることにしています。
そして再確認しながら答えをあとでマークシートに記入。
試験時間は90分。
つまり10時15分開始、11時45分終了の予定です。
試験が始まって退出可能時間になるまでの30分が勝負 だと思っています。
だと思っています。
試験開始後30分経過したら2級・3級受験の場合、どんどんと人が退出していきますので、
結構気がちってしまって注意力が散漫になってしまいます。
だれも退出しないこの30分のシーンとした時間に、
いかに集中力を上げるかが決め手になってくると考えます。
マークシートの欄を私はついつい性格柄几帳面に塗りつぶしたくなり、
そうなるととても時間がかかるためあとまわしに。
マークシートに記入していきながら問題を解いていくという方法をとったら
私の場合この最初の30分では最後まで解ききれないからです。
はじめの30分で如何に冷静に100問目まで解けるか。
なのでこの方法で試験に取り組んでいます。
ゆ〜っくりと再確認しながらマークシートに書き込んで。
あとどうしてもわからない・どっちか迷う問題があるので考えること数分ずつ。
3級といえども結構ぎりぎりまでは粘っていますが、
最後はまた退出しては駄目な時間(10分だったかしら?)があり
そこまではさすがに粘れずに出てくるというのが通常のパターンです。
3級とは反対に1級受験は退出可能の30分が経過しても殆どの方が出ていきません。
そう、大体この90分では時間が足らない人が大抵だからです
たまに出ていっている人を見かけますが、そういう方はよほどのきれる方か、試験を捨てた方か、体調が悪くなった方?
と私は思っています。
90分の割り振りとしては、はじめの30分で記述式設問1〜5(1問2点配点)の50問と設問6と7。
飛ばし飛ばしでもわかるところは答案用紙にざっと書きこむ。
後半の8.9.10の設問。
論文で問われるのは大体3つなので、1つの設問に約10分かける計算。
論文で問われている5個もしくは6個のことをプリントに箇条書きしたらすぐさま文章にして書いていく。
下書きをする時間はありません。
文章構成は小学生並みのものでもいい。とにかく書く。ひたすら書く。
箇条書きした5つか6つの言葉を漏らさず盛り込みながら
とにかく150字以上200字未満。多すぎても少なすぎてもだめ。
なにがなんでも規定のことはやる を心掛けています。
を心掛けています。
そして残りの30分で設問1〜7部分に戻り、わかるところからうめていく。
そんなこんなであっという間の90分を過ごします。
2.3級でも「えっ 」と思う問題はいくつかありますが
」と思う問題はいくつかありますが
1級となるとそう思う問題が多々有ります。
困難な問題にぶちあたっても、それを引きずらない。きっぱり捨てる。
わかるところを確実に押さえる。
1級では20%(およそ15問)、2.3級では30%(30問)間違えても
合格は合格なのですから、この際開き直りましょう
・・・・と偉そうに書きながら、実は自分に一番言い聞かせている私(^_^;)
本番は舞い上がってしまうのですよね
言うのは簡単、実行するのは本当に難しいです。
というか今はブログUPするより勉強しなさいって話ですね
やっぱり直前になっても熱が入ってない証拠
反省反省
試験まであと二日。用心しながらも頑張らないと

数年前に京都検定2・3級受験用に購入したもの

 マークシート専用のシャープペンシルと芯、そして消しゴム
マークシート専用のシャープペンシルと芯、そして消しゴム
別に普通のシャープペンシルや鉛筆でもいいのですが

「専用」という言葉に弱くて、こういう便利グッズについ手がのびてしまいました

これで記入するときちんと答えが繁栄されそうな気がします。
試験当日、3級は10時から各会場にて諸説明がはじまり、
マークシートの答案用紙に会場や受験番号もろもろを書き込み、
少しおいて大体10時15分あたりから試験開始です。
私の場合、まずは問題をざっと解き、答えと思われるものに○。
問題用紙プリントの四択の中の番号に直接○をつけています。
(こうしておくとあとで何に○をつけたか自己採点する際に都合がよい)
一通り解き終えたら最初のページに戻り、もう一度ゆっくりと確認。
四択の四つの言葉を一つずつしっかりと見て品定め。
案外思い込みや早とちりで最後までよく読まずにパパッと答えを判断していることがあり
後でよく考えると「なんでこの答えにしてしまったんだろう」と後悔すること多し。
なのでこのときに本当にそれで間違いがないかどうか、
四つをしっかりとみることにしています。
そして再確認しながら答えをあとでマークシートに記入。
試験時間は90分。
つまり10時15分開始、11時45分終了の予定です。
試験が始まって退出可能時間になるまでの30分が勝負
 だと思っています。
だと思っています。試験開始後30分経過したら2級・3級受験の場合、どんどんと人が退出していきますので、
結構気がちってしまって注意力が散漫になってしまいます。
だれも退出しないこの30分のシーンとした時間に、
いかに集中力を上げるかが決め手になってくると考えます。
マークシートの欄を私はついつい性格柄几帳面に塗りつぶしたくなり、
そうなるととても時間がかかるためあとまわしに。
マークシートに記入していきながら問題を解いていくという方法をとったら
私の場合この最初の30分では最後まで解ききれないからです。
はじめの30分で如何に冷静に100問目まで解けるか。
なのでこの方法で試験に取り組んでいます。
ゆ〜っくりと再確認しながらマークシートに書き込んで。
あとどうしてもわからない・どっちか迷う問題があるので考えること数分ずつ。
3級といえども結構ぎりぎりまでは粘っていますが、
最後はまた退出しては駄目な時間(10分だったかしら?)があり
そこまではさすがに粘れずに出てくるというのが通常のパターンです。
3級とは反対に1級受験は退出可能の30分が経過しても殆どの方が出ていきません。
そう、大体この90分では時間が足らない人が大抵だからです

たまに出ていっている人を見かけますが、そういう方はよほどのきれる方か、試験を捨てた方か、体調が悪くなった方?
と私は思っています。
90分の割り振りとしては、はじめの30分で記述式設問1〜5(1問2点配点)の50問と設問6と7。
飛ばし飛ばしでもわかるところは答案用紙にざっと書きこむ。
後半の8.9.10の設問。
論文で問われるのは大体3つなので、1つの設問に約10分かける計算。
論文で問われている5個もしくは6個のことをプリントに箇条書きしたらすぐさま文章にして書いていく。
下書きをする時間はありません。
文章構成は小学生並みのものでもいい。とにかく書く。ひたすら書く。
箇条書きした5つか6つの言葉を漏らさず盛り込みながら
とにかく150字以上200字未満。多すぎても少なすぎてもだめ。
なにがなんでも規定のことはやる
 を心掛けています。
を心掛けています。そして残りの30分で設問1〜7部分に戻り、わかるところからうめていく。
そんなこんなであっという間の90分を過ごします。
2.3級でも「えっ
 」と思う問題はいくつかありますが
」と思う問題はいくつかありますが1級となるとそう思う問題が多々有ります。
困難な問題にぶちあたっても、それを引きずらない。きっぱり捨てる。
わかるところを確実に押さえる。
1級では20%(およそ15問)、2.3級では30%(30問)間違えても
合格は合格なのですから、この際開き直りましょう

・・・・と偉そうに書きながら、実は自分に一番言い聞かせている私(^_^;)
本番は舞い上がってしまうのですよね

言うのは簡単、実行するのは本当に難しいです。
というか今はブログUPするより勉強しなさいって話ですね

やっぱり直前になっても熱が入ってない証拠

反省反省